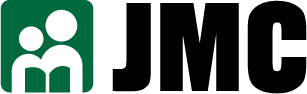- 課題
-
- 創造的・協働的な活動ができる空間を作りたい
- 余裕教室などの空間を有効活用したい
- 導入製品・サービス
-
- 学びの空間デザイン「新たな部屋」
- 自治体規模
- その他
- プロフィール
-
聖学院中学校・高等学校
東京都北区中里3-12-1
https://www.seigakuin.ed.jp/
- 印刷用資料
- ダウンロード(PDF:620KB)
- 取材日
- 2025年1月
聖学院中学校・高等学校(以下、聖学院)では、最新の設備が整った「フューチャーセンターA・B・C」が稼働しています。2024年12月、PCルームとして使っていた「フューチャーセンターC」に、JMCが提案する「新たな部屋」を導入し、リニューアルしました。導入の経緯や今後の活用法について、情報科主任・山本先生と教務部長・ICT担当の宮先生にお話を伺いました。
フューチャーセンターの完成を目指して、第三の部屋を整備
「フューチャーセンターC」に「新たな部屋」の導入を発案し、コンセプトをデザインしたのは山本先生です。「十数年来、この部屋はデスクトップPCを置いた机が並ぶ、PCルームでした。3年前のカリキュラム変更を機に、モバイルノート端末に替えたことで、机上で使う必要がなくなったのです。そして、一つの用途ではなく、汎用性のある空間にすることが、当校のモットーである多彩な学びの実現につながると考えました」。
「フューチャーセンター」創設時の立ち上げメンバーでもあった宮先生
はこう話します。「一方通行型から双方向型への授業形態の転換を促進するため、2016年に従来型の視聴覚教室・LL教室を、アクティブラーニングやプレゼンテーションに使える『フューチャーセンターA・B』にリニューアルしました。『フューチャーセンターC』も同時に変えたかったのですが、予算などの兼ね合いで保留になっていたのです。今回、満を持してリニューアルする『フューチャーセンターC』に『新たな部屋』を導入し、未来の学びを体験できる『フューチャーセンター構想』が完結しました」。

汎用性のある空間を目指し、提案以外の什器や設備をセレクト

「フューチャーセンターC」を実現する上で、重視した点は何だったのでしょうか。「A、Bとの連結性はもちろん、プレゼンテーションが自由にできること、その時々に応じた学びの場を提供できる空間にこだわりました。さらに、 私自身は企業や外部の方と連携しながら授業をつくる取り組みをしており、そういうことをプロトタイプとして試せる場を目指しました」(山本先生)。
2024年の1学期から「フューチャーセンターC」のリニューアルがスタート。山本先生は、打ち合わせもスムーズに進んだと語ります。
「JMCにすべてお任せするのではなく、企業連携を踏まえて、机やプロジェクターなどは、当校とお付き合いのある企業の製品を採用しました。その点でもJMCには柔軟に対応をいただきました」。「本当は丸ごとJMCにお願いした方が、お互いの手間が省けたと思います。ただ、我々自身で複数企業の製品を比較検討し、選定するプロセスを経たことで、より理想的な空間を実現できました。当校は木が基調なので、あえて壁を黒にして、クールで異質な空間に仕上げました。」(宮先生)。

英語の選択授業で活用し、放課後は生徒に開放
12月の初旬、待ちに待った「フューチャーセンターC」が完成しました。宮先生は思い描いた通りの「多機能な部屋」になったと顔をほころばせます。「汎用性と稼働性を兼ね備えているので、いろいろな使い方ができます最初。に完成した部屋を見た時は感動しました(笑)」。「イメージ通りで、かっこいい空間というのが最初の印象です。朝は、この窓辺から、生徒の登校風景を見るのが楽しみになりました。事前に告知した一部の生徒は、みんな待ち遠しい感じで、完成した時は大喜びでした」(山本先生)。
生徒も先生も使える、オープンな部屋にしたいと山本先生は話します。「20人くらいのキャパシティなので、発表が多い英語の選択授業に向いていると思います。聖学院では、OBや都内の大学生、企業などとコラボして『グローバル・イノベーション・ラボ(GIL)』というワークショップを開催しているので、そういう授業でも活用していく予定です。そして、放課後は、生徒たちがミーティングしたり、Yogiboに座って作業をしたり…と、自由に使ってほしいですね」。

さらに拡張性を持たせ、教育のアップデートに対応
今後の「フューチャーセンターC」の活用について、宮先生はこう語ります。「教育手法やトレンドは常に変化しています。また、教育というものは短期的成果だけでなく、中長期的な視点に立つことがとても重要だと思います。数年経って、『この空間でこういう授業をやったのが良かった』と分かるのではないでしょうか。この部屋にどのような拡張性を持たせて、どう実現していくのか。まさに、我々の腕の見せ所だと思っています」。
一方、山本先生は新たな目標が見えてきたと話します。「学習と研究は、両軸で回すべきだと思っています。授業をして終わりではなく、生徒からのフィードバックや教育者としての視差を残していくことが大切なので、少しアカデミックな文脈で使っていきたいです。例えば、連携する企業の新製品を展示して、生徒や先生の使用感や生の声をリサーチするとか、プロモーションやコミュニケーションに活用できれば良いですね」。
「新たな部屋」の導入を考えている学校に向けて、宮先生からアドバイスをいただきました。「最初に旗を振る先生は必要ですが、コンセプトをしっかり考えて、学校全体のコンセンサスを取って、進めていくことが大事です。学校の教育方針や目指す活動内容と、いかにリンクしているか。これが『新たな部屋』の成否を分けるポイントだと思います」。